1964年の東京オリンピック前年から放送が始まったNHK大河ドラマ。
そこで今回は、NHK大河ドラマ全タイトルと歴代主役俳優を一覧にしてご紹介いたします。
大河ドラマ歴代主役俳優一覧
2020年代
61作『鎌倉殿の13人(2022年)』
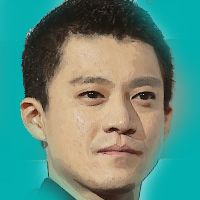 北条義時
北条義時
(小栗旬)
源平合戦が行われた華やかで雅な鎌倉時代を舞台に、源頼朝に学び武士の地位を築いた北条義時(小栗旬)。13人の家臣たちのパワーゲームを勝ち抜いた北条義時の半生を、脚本家・三谷幸喜がユニークに描きます。
60作『青天を衝け(2021年)』吉沢亮
 渋沢栄一
渋沢栄一
(吉沢亮)
新紙幣の“顔”として注目される「資本主義の父」と呼ばれた渋沢栄一を演じる吉沢亮。多くの会社や組織を生み出し、国益を優先しながら近代日本を駆け抜けた渋沢の生涯の物語。
59作『麒麟がくる(2020年)』長谷川博己
 明智光秀
明智光秀
(長谷川博己)
「仁」のある政治を行う君主の前に現われるという伝説の聖獣「麒麟」。その麒麟が現れる戦のない穏やかな世を望む武将の名は、明智光秀(長谷川博己)。光秀は後に、織田信長(染谷翔太)に仕え“戦国時代随一”の智将として知られるように。そんな謎めいた明智道秀の半生にスポットを当て、波乱に満ちた人生を中心に、戦国の英傑たちの生き様を描いた。
歴代・明智光秀を演じた俳優は⇒こちら
2010年代
58作『いだてん(2019年)』中村勘九郎
 金栗四三
金栗四三
(中村勘九郎)
初めてオリンピックに出場した金栗四三と、戦後、東京オリンピック誘致に尽力した田畑政治を中心とした日本人とオリンピックの歴史を描いた物語。
57作『西郷どん(2018年)』鈴木亮平
 西郷隆盛
西郷隆盛
(鈴木亮平)
出会うもの誰もが惚れる人たらし西郷隆盛。二度の島流しにもめげず、明治維新を成し遂げながら、最後は新政府と戦わざるえなかった西郷どんの生涯。
56作『おんな城主 直虎(2017年)』柴咲コウ
 井伊直虎
井伊直虎
(柴咲コウ)
近江・井伊谷で「直虎」という男の名で家督を継いだ一人の姫が。幼い跡継ぎ・虎松(のちの井伊直正)を守り、戦国をたくましく生き抜く。
55作『真田丸(2016年)』堺雅人
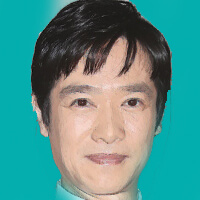
真田信繁
(堺雅人)
信州の真田信繁が、大阪の陣では「真田幸村」として敵方の徳川勢から“日本一の兵”とたたえられる武将になるまでの姿を描いた。
54作『花燃ゆ(2015年)』井上真央
 杉文
杉文
(井上真央)
吉田松陰の妹として、そして武士の妻として幕末を生き抜き、明治維新後は産業の発展に尽くす群馬県知事を支えた文(ふみ)の力強い人生。
53作『軍師官兵衛(2014年)』岡田准一
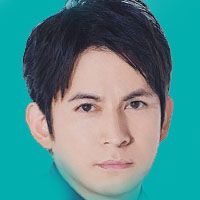 黒田官兵衛
黒田官兵衛
(岡田准一)
天才軍師として秀吉を天下人に押し上げるが、その才能ゆえに秀吉からも警戒された黒田官兵衛の夢と野望を描いた。
52作『八重の桜(2013年)』綾瀬はるか
 新島八重
新島八重
(綾瀬はるか)
会津では銃を手に新政府軍と戦い、維新後は新島襄の妻として共に新しい時代を歩み、戦争で傷ついた兵士の看護にもあたった八重の人生。
51作『平清盛(2012年)』松山ケンイチ
 平清盛
平清盛
(松山ケンイチ)
武士として初めて支配者となった平清盛。「平家物語」では悪者として描かれた平清盛を、武家社会の礎を築いた変革者、海外貿易の先駆者として新しい視点で描いた。
50作『江 〜姫たちの戦国〜(2011年)』上野樹里

江
(上野樹里)
織田信長は伯父、父は織田信長に殺された浅井長政。3姉妹の末っ子・江(ごう)は、戦国の世に翻弄されながらも、徳川二代将軍・秀忠に嫁ぎ、平和な世を願う。
49作『龍馬伝(2010年)』福山雅治
 坂本龍馬
坂本龍馬
(福山雅治)
薩長同盟や大政奉還の立役者となる土佐脱藩浪士・坂本龍馬の33年に生涯を同郷で、三菱財閥の創始者・岩崎弥太郎の回想という形で描いた。
歴代・坂本龍馬を演じた俳優ランキングは⇒こちら
2000年代
48作『天地人(2009年)』妻夫木聡
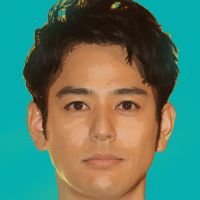
直江兼続
(妻夫木聡)
5歳で上杉謙信の家臣となり、生涯にわたって主君に忠誠を尽くした直江兼続の生涯。義を貫き、仁愛を重んじる兼続は、秀吉、家康らも魅了した。
47作『篤姫(2008年)』宮﨑あおい
 天璋院
天璋院
(宮崎あおい)
薩摩藩から将軍家に嫁ぐが、夫・家定は急死。幕府が崩壊していくなか、大奥の最高実力者として最後まで徳川家のために生きた篤姫の一生。
46作『風林火山(2007年)』内野聖陽
 山本勘助
山本勘助
(内野聖陽)
戦国最強とうたわれた甲斐の国の武田信玄に仕え、主君の宿敵・上杉謙信との戦いに命をかけて散った伝説の軍師・山本勘助の夢と野望に満ちた生涯。
45作『功名が辻(2006年)』仲間由紀恵/上川隆也
 千代
千代
(仲間由紀恵)
嫁入りの持参金で、貧しい夫に しゅんめ をかわせたことが立身のきっかけになった。という逸話を残した山内一豊の賢妻・千代の内助の功を描いた。
44作『義経(2005年)』滝沢秀明
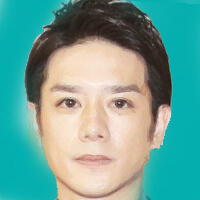
源義経
(滝沢秀明)
父親を殺した平清盛を一度は「父」と慕い、やがて平家滅亡に決定的な役割を果たすも、奥州で悲劇的最期を遂げた源義経の愛と悲劇の生涯。
43作『新選組!(2004年)』香取慎吾
 近藤勇
近藤勇
(香取慎吾)
「誠」の旗をかかげ、幕末動乱の最前線で刃をふるい続けた新選組局長・近藤勇と副長・土方歳三など若き隊士たちの短くも鮮烈な青春群像劇。
42作『武蔵 MUSASHI(2003年)』市川新之助
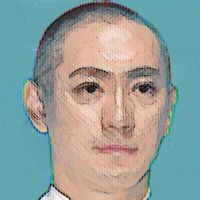 宮本武蔵
宮本武蔵
(市川新之助)
巌流島の決闘を含め、生涯敗れたことがないという剣豪・宮本武蔵が、人間としての弱さを克服しながら剣の道を追求する姿を描いた。
41作『利家とまつ(2002年)』唐沢寿明/松嶋菜々子
 前田利家
前田利家
(唐沢寿明)
夫婦でともに加賀百万石の基礎を作った前田利家と、妻・まつのサクセスストーリー。まつの決め台詞「わたくしにお任せくださりませ」もブームとなった。
40作『北条時宗(2001年)』和泉元彌

北条時宗
(和泉元彌)
18歳の若さで鎌倉幕府の執権となった北条時宗。壮絶な権力闘争や、2度にわたる“国難”蒙古襲来に、果敢に立ち向かった34年の波乱万丈の生涯を描いた。
39作『葵 徳川三代(2000年)』津川雅彦/西田敏行/尾上辰之助
 徳川秀忠
徳川秀忠
(西田敏行)
徳川家の家紋「三つ葉葵」を家康(津川雅彦)、秀忠(西田敏行)、家光(尾上辰之助)の心の絆になぞらえた徳川三代の物語。
1990年代
38作『元禄繚乱(1999年)』中村勘九郎
 大石内蔵助
大石内蔵助
(中村勘九郎)
太平元禄の起こった浅野内匠頭の松の廊下の傷によって起こった大事件の人間ドラマを大石内蔵助を中心に描いた。吉良上野介を石坂浩二が演じた。
37作『徳川慶喜(1998年)』本木雅弘
 徳川慶喜
徳川慶喜
(本木雅弘)
水戸徳川家から30歳で15代将軍となるが、倒幕の波にあらがいきれず、武家政治に幕を引いた最後の将軍・徳川慶喜の波乱の半生。
36作『毛利元就(1997年)』中村橋之助

毛利元就
(中村橋之助)
“三矢の教え”で有名な毛利元就の生誕500年を記念して放送。27歳で毛利家を相続、西日本最大の大名になった元就を人間味あふれるストーリーで描いた。
35作『秀吉(1996年)』竹中直人
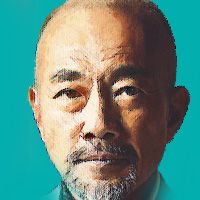 豊臣秀吉
豊臣秀吉
(竹中直人)
貧しい農民の子から、天下人に登り詰めた豊臣秀吉の出世物語を、組織に生きる現代のサラリーマンとリンクするように描いた。秀吉のセリフ「心配ご無用」も人気に。
【歴代・豊臣秀吉役一覧】ハマっていた俳優ランキングは⇒こちら
34作『八代将軍吉宗(1995年)』西田敏行
 徳川吉宗
徳川吉宗
(西田敏行)
紀州藩主の四男・吉宗は、強運によって将軍の座につき、幕府改革で名声を得ていく。近松門左衛門(江守徹)が解説者として登場したことも話題に。
33作『花の乱(1994年)』三田佳子

日野富子
(三田佳子)
室町幕府後期、政治にかかわり、応仁の乱の原因をつくり“希代の悪女”と呼ばれた八代将軍・足利義政の妻・日野富子の人物像に迫った作品。
32作『炎立つ(1993年)』渡辺謙/村上弘明
 藤原経清
藤原経清
(渡辺謙)
平安時代末期、東北の平泉に栄えた奥州藤原氏の100年の浮き沈みを、祖・藤原経清から源頼朝、滅ぼされる泰衡までの三部構成で描いた。
31作『琉球の風(1993年)』東山紀之
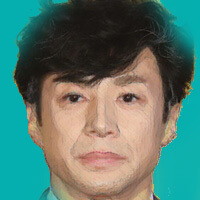
楊啓泰
(東山紀之)
独立国家琉球に侵攻してくる薩摩藩に立ち向かう人々の姿を、啓泰、啓山の兄弟を中心に描いた。大河ドラマ初の主題歌を谷村新司が歌った。
30作『信長(1992年)』緒形直人
 織田信長
織田信長
(緒形直人)
型破りな暴君としてのイメージがある織田信長を、一宣教師の目線の回想という形で描いた。緒方直人が繊細な信長を演じた。
29作『太平記(1991年)』真田広之
 足利尊氏
足利尊氏
(真田広之)
鎌倉幕府滅亡から、南北朝の動乱期を室町幕府将軍・足利尊氏を中心に描いた。大河ドラマで、南北朝がテーマとなったのは初めてだった。
28作『翔ぶが如く(1990年)』
 西郷隆盛
西郷隆盛
(西田敏行)
明治への大変革期を二人三脚でリードした薩摩藩家臣・西郷隆盛、大久保利通の友情と対立、そして近代国家づくりに奔走した人々を描いた。
1980年代
27作『春日局(1989年)』大原麗子
 春日局
春日局
(大原麗子)
父は明智光秀の側近。母と戦国動乱を生き延び、徳川三代将軍・家光の乳母として、そして大奥取り締まりとして幕府創成期を支えた春日局を描いた。
26作『武田信玄(1988年)』中井貴一
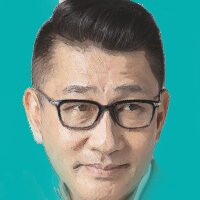
武田信玄
(中井貴一)
戦国最強“甲斐の虎”と称された武田信玄の戦いに明け暮れた激しい生涯。若尾文子の語る「今宵はここまでにいたしとうござりまする」は流行語にもなった。
25作『独眼竜政宗(1987年)』渡辺謙
 伊達政宗
伊達政宗
(渡辺謙)
仙台初代藩主・伊達政宗の生涯。子ども時代の政宗のセリフ「梵天丸もかくありたい」が流行語に。平均視聴率39.8%は歴代大河ドラマ最高。
24作『いのち(1986年)』三田佳子
 岩田未希
岩田未希
(三田佳子)
終戦の混乱のなか、母をガンで亡くした悲しみから医師となった未希は、妻・母・嫁としての葛藤を抱えながら、人の“いのち”と向き合った。
23作『春の波涛(1985年)』松坂慶子

川上貞奴
(松坂慶子)
明治・大正の時代を背景に、日本の女優第一号として海外でも活躍した川上貞奴と、彼女を取り巻く起伏にとんだ人間模様を描いた。
22作『山河燃ゆ(1984年)』松本幸四郎/西田敏行
 天羽賢治
天羽賢治
(松本幸四郎)
2つの祖国を持つ日系アメリカ人2世の天羽兄弟とその家族を中心に、昭和初期から戦後の激動の時代を日本・アメリカを舞台に描いた。
21作『徳川家康(1983年)』滝田栄
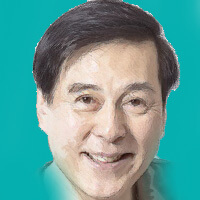
徳川家康
(滝田栄)
戦乱の世を知恵と忍耐で最後に勝ち残り、260年続く平和な世の基礎を築いた徳川家康。その波乱に満ちた75年の生涯を浮き彫りにした。
20作『峠の群像(1982年)』緒形拳
 大石内蔵助
大石内蔵助
(緒形拳)
江戸元禄の繁栄と現代にも通じる武士や町人の生き方を、赤穂浪士の討ち入りを軸に描いた。吉良上野介を伊丹十三が演じた。
19作『おんな太閤記(1981年)』佐久間良子

ねね
佐久間良子
足軽から天下人に登り詰めた豊臣秀吉の正室・ねねの視点から、秀吉、信長や女性たちを描いた斬新な戦国大河。脚本は橋田寿賀子。
18作『獅子の時代(1980年)』菅原文太/加藤剛
 平沼銑次
平沼銑次
(菅原文太)
明治維新の前夜1867年パリ万博で出会った会津藩と薩摩藩の下級武士2人を通して、明治初期の日本を描いた。宇崎竜童が手掛けた音楽も話題となった。
1970年代
17作『草燃える(1979年)』石坂浩二

源頼朝
(石坂浩二)
鎌倉幕府を開いた源頼朝から頼家、実朝の源氏三代と、頼朝の妻・北条政子(岩下志麻)を中心に武家政権への転換期を描いた。頼朝の死後は北条政子が主人公になった。
16作『黄金の日日(1978年)』市川染五郎
 呂宋助左衛門
呂宋助左衛門
(市川染五郎)
戦国末期、海外貿易を開いた豪商・呂宋助左衛門の活躍を、経済的視点も交え描いた。大河ドラマでは初めて海外(フィリピン)ロケを行った。
15作『花神(1977年)』中村梅之助
倒幕の戦で活躍し、日本の近代兵制の創始者と言われた長州藩の大村益次郎と、高杉晋作ら維新に力を尽くした若者たちの群像劇。
14作『風と雲と虹と(1976年)』加藤剛

平将門
(加藤剛)
平安中期、貴族の世にあらがって民衆のための国を目指した平将門と、藤原純友ら将門をめぐる人間模様を描いた。歴代の大河ドラマでも、最も古い時代が舞台となった。
13作『元禄太平記(1975年)』石坂浩二

柳沢吉保
(石坂浩二)
五代将軍の徳川綱吉の使用人として、取り仕切った柳沢吉保(石坂浩二)の栄光と挫折を、武士の生き方を貫いた大石内蔵助(江守徹)との対立を主軸に描いた。
12作『勝海舟(1974年)』渡哲也→松方弘樹

勝海舟
(渡哲也)
明治維新前夜、日本海軍の基礎を築き江戸城を無血開城に導いた幕臣・勝海舟の半生。渡哲也の急病によって、松方弘樹が主演を引き継いだ。
大河ドラマ歴代の降板俳優一覧は⇒こちら
11作『国盗り物語(1973年)』平幹二朗/高橋英樹

織田信長
(高橋英樹)
下剋上で大名となった“美濃の蝮”斎藤道三(平幹二郎)を主人公に、織田信長(高橋英樹)が明智光秀に討たれるまでの波乱の戦国時代を描いた。
10作『新・平家物語(1972年)』仲代達矢

平清盛
仲代達也
平家一門の栄華を築き上げた平清盛を中心に、盛者必衰の運命をたどり壇ノ浦で滅亡した平氏を現代的に描いた作品。
9作『春の坂道(1971年)』中村錦之助
戦乱から太平へ転換した時代、剣の道を極め徳川三代に仕えた柳生宗矩の生涯。山岡荘八の同名小説はベストセラーとなった。側室を松本留美が演じた。
8作『樅ノ木は残った(1970)』平幹二朗
江戸時代前期の仙台藩の伊達騒動(お家騒動)を元に、逆臣の汚名を着せられながらお家安泰に尽くした家老・原田甲斐を描いた。
1960年代
7作『天と地と(1969年)』石坂浩二

上杉謙信
(石坂浩二)
“越前の龍”と称された上杉謙信を石坂浩二が演じた。石坂は3作目の『太閤記』で石田三成を演じ人気となり本作で主役に大抜擢された。
6作『竜馬がゆく(1968年)』北大路欣也
 坂本龍馬
坂本龍馬
(北大路欣也)
土佐の脱藩浪士でありながら、薩長同盟の実現に奔走し、新しい時代を夢見て幕末を駆け抜けた竜馬の生涯。風雲児である竜馬の妻・おりょうを浅丘ルリ子が演じた。
5作『三姉妹(1967年)』岡田茉莉子/藤村志保/栗原小巻

むら
(藤村志保)
幕末から明治維新の波乱の時代を、旗本の三姉妹と一人の浪人(山崎努)の姿を通して描いた。大河ドラマでは珍しく架空の人物が主人公となった。
4作『源義経(1966年)』尾上菊之助

源義経
(尾上菊之助)
平氏が滅びた戦で伝説に残る活躍をみせたが、やがて実兄の頼朝に追われ悲劇的な最期を迎えた義経の短い生涯を描いた物語。弁慶には前作の主役だった緒形拳が起用された。
3作『太閤記(1965年)』緒形拳
 豊臣秀吉
豊臣秀吉
(緒形拳)
織田信長に目をかけられ、やがて太閤になる豊臣秀吉の生涯。前2作とは違い、まだ無名だった緒形拳、織田信長を演じた高橋幸治が抜擢された。二人はこの作品で知名度をあげた。
2作『赤穂浪士(1964年)』長谷川一夫
大石内蔵助が率いる赤穂浪士たちが主君である浅野内匠頭の仇討ちのために吉良上野介を狙う。戦前からのスター長谷川一夫が演じ、最高視聴率53%を叩き出した。
1作『花の生涯(1963年)』尾上松緑
彦根藩主から大老になり、幕府存続に尽力するも、桜田門外に倒れた井伊直弼の生涯を、歌舞伎界のスター尾上松緑が見事に演じた。
最後に
大河ドラマの長い歴史で、多くの俳優が主役を演じスターが誕生してきました。
一年をかけて物語を紡いでいく大河ドラマは、これからも長く続いてほしいですね。




